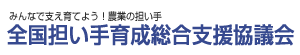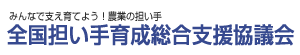有限会社良品工房
白田典子
「この498 円のイチゴとあの348 円のイチゴはどう違うの?」と店先で聞きたいときがある。こんなときは、近所の八百屋のおじさんなら「粒の大きさだけだよ。味は変わらないよ」とすぐに返事をしてくれる。だから時と場合によって、どちらを買えばいいかがすぐに判断できる。
ところがスーパーでは売り場に声をかける人も滅多に見かけないし、いたとしてもなかなか即答できる人はいない。だから私たちは商品のパッケージや店頭のPOP に書いてあることを買い物の判断材料にするしかないのだが、実はこれがあまり役に立っていない。
私の会社が推進している「いいものプロジェクト」のモニターさんたちに「買い物していてわからないなあと感じることを教えてください」と尋ねてみた。
「白い卵と肌色の卵、生食用と書いてある卵はどう違うの?」
「600 グラム198 円と4 個198 円のジャガイモはどっちがお得なんだろうと、店先で迷ってしまう」
「お豆腐を買うときに迷います。どれも国産大豆、にがり使用と書いてあり、大きさも同じ。違うのは値段だけで、中身の違いがわからない」
卵やジャガイモ、お豆腐などふだんよく買うものですら、わからないことがいっぱいあるのだから、買う頻度の少ないものになると、さらに私たちの「わからない」は倍増する。
「オリーブオイルを買うときに、どれを選んでいいのかわからなくて、いつも困るのよ」
「そうそう、高いものから安いものまで値段にかなりの幅があるから、適当に真ん中くらいの値段のものを買っちゃってる」
「わからない」には、価格に関するコメントも多かった。
「99 円セールなどとありますが、これって本当に普段売っている中身のままなのでしょうか?それともだれかが損をしているのでしょうか?」
「冷凍食品って、どうしていつも3 割、4 割引きにできるんですか?」
もちろん安いのは主婦にとってうれしいことには違いないが、「なんでそんなに、しかもしょっちゅう安くなるわけ?」と不思議に思いながら買い物をしている人も実は多いのだ。
いったい価格はどうやって決まるのか。単純に考えると大量に仕入れる場合のほうが安くなる・・・ということになるのだろうが、実際にいろいろなお店を見比べてみると、全国チェーンの大型店がなんでも安いというわけでもない。
あるとき、いつも行くスーパーで200 円で買っている高知産のショウガが、近所の八百屋さんで100 円で売られているのを発見した。
「なんでこんなに値段が違うの?」と聞いてみると、笑いながらこう答えてくれた。
「スーパーさんは毎日必ずそのショウガを揃えておかなきゃいけないだろ。でも、うちらは相場が高いときはやめとことか、モノがよくないときには仕入れはやめとことか自分で判断できるからね。その代わりうちはいつも同じショウガじゃなかったりするわけよ」
「同じ大福が30 円も高いのよ!」とはある宅配会社を利用しているモニターさんの談。
お店で買っていたものと同じ大福をその宅配会社のカタログでたまたま発見し、その会社のほかの商品に対しても「他のお店より高いんじゃないの?」と不信感を持ったそうだ。
言われてみれば「な〜るほど」とうなずける部分、「え−っ、そんなことがわからなかったの?」と驚く部分も多いのではないだろうか。
私たちが価格をみて思うのは、単に高いとか安いとかということだけではない。
「安いのは中身がよくないから?それともだれかが損をしているの?」
「同じ商品が他のお店より高いのは、必要以上に儲けているからなんじゃないの?」といつも「???」な気持ちで買い物しているのだ。価格の裏側にある理由やカラクリ、それをはっきりさせてくれないとスッキリした気持ちで買い物ができない。
生産者と消費者はお互いの顔を見たいと望んでいる。これは言い換えればお互いの距離が遠い、という現実。お互いにわからないことが多いということだ。拠りどころなく生産し、拠りどころなく買い物をしているということだ。
「わからない」は価格に限ったことではないし、消費者だけが「わからない」を抱えているわけでもない。
もともと、商品とお客をマッチングさせるのが中間業者の仕事だったと思う。ところがいつのまにか間に入ることで、お互いを遠ざけてしまったような気がする。中間業者に限らず広告会社もマーケティング会社もデザイン、パッケージ会社も生産者と消費者を遠ざけてしまったのではないかと感じる。
©日本農業法人協会
|