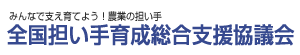
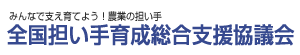 |
|
| トップページ > 農業法人について > 農業法人経営情報 > 有限会社 伊豆沼農産 伊藤秀雄さん | ||||||
 伊藤秀雄さん |
「日本の農業の将来方向が決まる重要な協議ですので、もう少しお待ちください」昨年6月の日本農業人法人協会総会で、議事を中断して開かれた役員懇談会が予定より長引いていた時に、議長を務めていた伊藤氏が会場に向かってそう呼びかけた。それは単に待たされる側をなだめようとしたからではない。協議が真にそうであって欲しいと思ったからに違いないし、法人組織の将来でもなければ法人経営の将来でもなく「日本の農業の将来方向」としたのは、担い手としての自負と責任感からであろう。
1985年ラムサール条約で保護地域に指定された伊豆沼と東北本線をはさんで向かい合う格好で本拠は位置する。指定直後は内外から学者、マスコミ等が大挙して押しかけるなど、サンクチュアリー(聖域)ゆえに「農業をやりづらい雰囲気を感じないでもなかった」。しかしそのころから「農業とは?」あるいは「経営とはいかにあるべきか」等々自問する日々が始まる。
答として浮かんだのは「農業を"食業"に変える」という基本的な方向付け。単純な"もの"の供給から加工、販売への進出を図った。だがそこまではいうなれば「農業の範疇内」のことである。次第に「農業、経営というだけでは語り尽くせない事柄の多さ、複雑さに気づくようになる」。そして今日では自分の中で"もの"に加えて"人"と"環境"とが重きをなそうとしている。
その出発点というべきが「地域産業としてのあり方」。どのような中身が地域産業として最良かというのである。結論は「身近に埋もれている宝物を発掘してみること。それらを有機的に組み合わせれば、農村地域にしかできない産業を構築できる」と出た。伊豆沼農産には1次産業部門から3次までの、全てが備わっている。しかしこれら3部門は"食"(=もの)という概念だけで組み合わせられているに過ぎない。伊豆沼には独自の歴史があり、豊かで他に類を見ない自然環境があり、ものづくりの名人もいる。「それらの組み合わせによって、ここ伊豆沼にしかない、オンリーワン産業を創出しよう」とのグランド・デザインが描かれている。ここ数年はその具体化に夢中。「あれこれ思いめぐらせていると面白くてたまらない」。
現在の経営では水稲30ha、ブルーベリー30aなど耕種作物の生産・販売のほかに、大きな地位を占めるのが『伊達の純粋赤豚』だ。
 伊豆沼農産の販売施設内で |
昔からの養豚仲間8戸を組織し、精肉と関連加工商品を販売している。特に精肉は需要を完全に満たせないほど好評で、それを支えるのは「年間平均で1,600頭。入荷する全頭についての社内試食」である。一般的な格付とは別に、3人の従業員による独自の評価で5段階の3以上でなければ「店頭には並べない」。この赤豚は直営レストランの『クンペル』でも食べることができる。そこで「美味しさに満足した客の足は自然と販売施設に向かう」のであって、ライバルの黒豚に「絶対勝つとは言わないまでも、絶対に負けないのも確か(笑)」。自信満々だ。
2004年7月には中国への輸出にも成功した。ブランドニッポン、わが国の農産物に対する東アジアが寄せる信頼性は高い。残念なのはそうした国産の農産物に対する価値を国内消費者はおろか農業者も理解していない点である。日本では安全は最早当たり前になっているが、他国ではまだその域に達しておらず、それが証拠に輸出された豚肉には100g800円という価格がついた。「国産の農産物に対する誇りを持つことが全ての農業者に望まれる」。
組織としての日本農業法人協会を今日のレベルにまで育て上げるため「数多くの先達が本来ならば自分の経営に割くべき労力と時間を捧げてきたことは間違いないところであり、そうした献身的な努力に感謝している」。伊豆沼農産も形こそ異なるが、「全国の農村に住む人たちに見に来ていただけるような雛形的な存在となるよう、そしてそれが農業経営と農村地域の活性化に役立つ情報発信の場となるよう努めていきたい」。新たな年を迎え、こうした想いは一層強まっている。
©日本農業法人協会